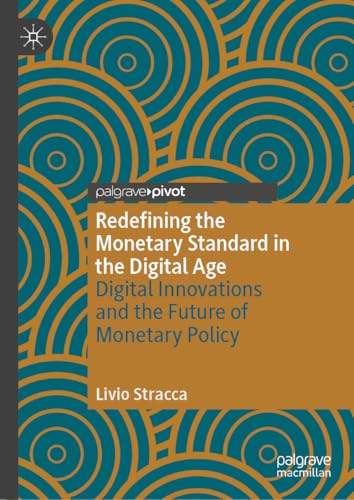ECB銀行ã®Livio Stracca*1ãŒã€ä»¥ä¸‹ã®è¿‘è‘—ã§æ示ã—ãŸç¾åœ¨ã®é‡‘èžçµŒæ¸ˆã«ãŠã‘る考察ã‹ã‚‰7ã¤ã‚’ピックアップã—ã¦è¡¨é¡Œã®VoxEUコラム(原題ã¯ã€ŒWhat money will become: Seven key questionsã€ï¼‰ã§提示している(H/T Mostly Economics)。
以下ã¯ãã®æ¦‚è¦ã€‚
- ç¾åœ¨ã¯é‡‘èžçµŒæ¸ˆã«ã¨ã£ã¦ä¸€ä¸–代ã®é–“ã§æœ€ã‚‚興味深ã„時ãªã®ã‹ï¼Ÿ
- 転æ›æœŸã¨ã„ã†æ„味ã§ã¯ã€ä¸æ›ç´™å¹£çµŒæ¸ˆã«ãŠã„ã¦ç‰©ä¾¡å®‰å®šã‚’é”æˆã™ã‚‹æŠ€è¡“ã‚’ä¸éŠ€ãŒä¼šå¾—ã—ãŸ1980年代åŠã°ã®å¤§å¹³ç©æœŸä»¥æ¥ã®èˆˆå‘³æ·±ã„時ã§ã¯ãªã„ã‹ã€‚
- デジタル資産ã®å°é ã«ã‚ˆã‚Šã€è²¨å¹£ã¨ã¯ä½•ã‹ã€èª°ãŒç™ºè¡Œã™ã¹ãã‹ã€ã¨ã„ã£ãŸæ ¹æœ¬çš„ãªå•é¡ŒãŒå•ã„ç›´ã•ã‚Œã¦ã„る。
- 準備é 金ã¸ã®åˆ©æ‰•ã„:ç¾ä»£ã®é‡‘èžæ”¿ç–ã«ãŠã‘る語られるã“ã¨ã®ãªã„å‰æ¥ï¼Ÿ
- ç¾ä»£ã®ä¸»è¦ãªé‡‘èžæ”¿ç–ã®ä½“ç³»ã¯1980年代ã«ç¢ºç«‹ã—ãŸãŒã€ä¸–界金èžå±æ©Ÿå¾Œã«ç±³å›½ã‚’ã¯ã˜ã‚ã¨ã™ã‚‹å…ˆé€²å›½ãŒå°Žå…¥ã—ãŸIORã¯ã€æ‰€è¦ãªã‚‰ã³ã«è¶…éŽæº–å‚™é 金ã«ä¸éŠ€ãŒé‡‘利を支払ã£ã¦å目金利を直接的ã«è¨å®šã§ãるよã†ã«ã—ãŸã¨ã„ã†ç‚¹ã§ä¸éŠ€ã®æ“作ã®æž 組ã¿ã«é©å‘½ã‚’ã‚‚ãŸã‚‰ã—ãŸã€‚
- 物価ã®å®‰å®šã«ä¿‚る金利ã¨ã€é‡‘èžã®å®‰å®šæ€§ã«ä¿‚ã‚‹é‡çš„ç·©å’Œã®æ°´æº–を(少ãªãã¨ã‚‚ã‚る程度)独立ã«è¨å®šã§ãるよã†ã«ãªã£ãŸã€‚ãã®ç‚¹ã§ã€IORã«ã‚ˆã‚Šä¸éŠ€ã¯æ¼¸ã「フリードマンルールã€ã«æ²¿ã†ã‚ˆã†ã«ãªã£ãŸã€ã¨è¨€ãˆã‚‹ã€‚
- ç¾åœ¨ã®é‡‘èžã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã¯çµ¶å¯¾ç¢ºå®Ÿã‹ï¼Ÿ
- ç¾åœ¨ã®é‡‘èžã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã¯éžå¸¸ã«ä¸Šæ‰‹ã機能ã—ã¦ã„ã‚‹ã‚‚ã®ã®ã€æ¬ 点や潜在的ãªè„…å¨ãŒç„¡ã„ã‚ã‘ã§ã¯ãªã„。
- ゼãƒé‡‘利下é™å•é¡Œ
- テイラー原ç†ãŒå°‘ãªãã¨ã‚‚ç†è«–上ã¯çˆ†ç™ºçš„ãªã‚¤ãƒ³ãƒ•ãƒ¬ä¸Šæ˜‡ã¨æ•´åˆçš„ã§ã‚ã‚‹ã“ã¨
- フィリップス曲線ã¨IS曲線ã«ãŠã‘ã‚‹ä¸ç¢ºå®Ÿæ€§ã®å¢—åŠ ã¨é‡‘利ã¸ã®å応度ã®ä½Žä¸‹ã«ã‚ˆã‚Šã€ã‚¤ãƒ³ãƒ•ãƒ¬ç›®æ¨™é”æˆã®å›°é›£åº¦ãŒå¢—ã—ãŸã“ã¨
- 自然利å率ã®è©•ä¾¡ã®é›£ã—ã•
- å„国ã®ã‚¤ãƒ³ãƒ•ãƒ¬ã«é–¢ã™ã‚‹ãƒ‘フォーマンスã¯ã€é‡‘èžæ”¿ç–ã®ãƒ†ã‚¯ãƒ‹ã‚«ãƒ«ãªè¦å› よりも制度ã®è³ªã‚’åæ˜ ã™ã‚‹*2。
- ç¾åœ¨ã®é‡‘èžã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã¯éžå¸¸ã«ä¸Šæ‰‹ã機能ã—ã¦ã„ã‚‹ã‚‚ã®ã®ã€æ¬ 点や潜在的ãªè„…å¨ãŒç„¡ã„ã‚ã‘ã§ã¯ãªã„。
- ç¾é‡‘ã®å‡‹è½ï¼šå¯¿ãã¹ãã‹ã€æ‡¸å¿µã™ã¹ãã‹ï¼Ÿ
- ãƒã‚´ãƒ•ï¼ˆ2016*3)ã®ã‚ˆã†ã«ã€ã‚¼ãƒé‡‘利下é™å•é¡Œã‚’継続ã•ã›ã€é•æ³•å–引をå¯èƒ½ãªã‚‰ã—ã‚ã‚‹è¦å› ã¨ãªã£ã¦ã„ã‚‹ç¾é‡‘ã®å‡‹è½ã¯å¿…ãšã—も悪ã„ã“ã¨ã§ã¯ãªã„ã€ã¨è«–ã˜ã‚‹çµŒæ¸ˆå¦è€…ã‚‚ã„ã‚‹ãŒã€ä»¥ä¸‹ã®ç‚¹ã‚‚考慮ã™ã¹ã。
- 今や完全ãªåŒ¿å性を確ä¿ã™ã‚‹æ”¯æ‰•ã„手段ã¯ç¾é‡‘ã®ã¿ã€ã¨ä¸»å¼µã™ã‚‹äººã‚‚ã„る。
- よりé‡è¦ãªã®ã¯ã€åœé›»ã€è‡ªç„¶ç½å®³ã€ã‚µã‚¤ãƒãƒ¼æ”»æ’ƒã¨ã„ã£ãŸå±æ©Ÿã«ãŠã‘る予備手段ã¨ã—ã¦ã®æ©Ÿèƒ½ã€‚
- ä¿¡é ¼æ€§ã‚’ç¶æŒã™ã‚‹ãŸã‚ã«ã€ç¾é‡‘ã¯æµé€šã‚’続ã‘ã¦å®Ÿä¸–ç•Œã®ç’°å¢ƒã§ç¶™ç¶šçš„ã«æ¤œè¨¼ã•ã‚Œã‚‹å¿…è¦ãŒã‚る。
- CBDCå°Žå…¥ã®å‹•ãã‚‚ç¾é‡‘ã®å‡‹è½ã¸ã®å¯¾å¿œã¨è¨€ãˆã‚‹ã€‚
- ãƒã‚´ãƒ•ï¼ˆ2016*3)ã®ã‚ˆã†ã«ã€ã‚¼ãƒé‡‘利下é™å•é¡Œã‚’継続ã•ã›ã€é•æ³•å–引をå¯èƒ½ãªã‚‰ã—ã‚ã‚‹è¦å› ã¨ãªã£ã¦ã„ã‚‹ç¾é‡‘ã®å‡‹è½ã¯å¿…ãšã—も悪ã„ã“ã¨ã§ã¯ãªã„ã€ã¨è«–ã˜ã‚‹çµŒæ¸ˆå¦è€…ã‚‚ã„ã‚‹ãŒã€ä»¥ä¸‹ã®ç‚¹ã‚‚考慮ã™ã¹ã。
- ビットコインã«ã¯æ¬ 点ãŒã‚ã‚‹ãŒã€ãã‚ŒãŒã‚‚ãŸã‚‰ã—ãŸé©å‘½ã«ã¯å®Ÿä½“çš„ãªä¾¡å€¤ãŒã‚ã‚‹ã®ã‹ï¼Ÿ
- ビットコインã®ãƒ–ãƒãƒƒã‚¯ãƒã‚§ãƒ¼ãƒ³æŠ€è¡“ã¯ã€ŒäºŒé‡æ”¯æ‰•ã„å•é¡Œ*4ã€ã‚’解決ã—ã€ä»²ä»‹ã‚’経由ã—ãªã„安全ãªä¸€å¯¾ä¸€ã®å–引をå¯èƒ½ã«ã—ãŸã€‚ã—ã‹ã—ã€ä»¥ä¸‹ã®2ã¤ã®ç†ç”±ã«ã‚ˆã£ã¦å°†æ¥ã®è²¨å¹£ã¨ã¯ãªã‚‰ãªã„ã ã‚ã†ã€‚
- 支払ã„システムãŒéžåŠ¹çŽ‡çš„
- éžé›†æ¨©çš„ãªæ€§è³ªã«ã‚ˆã‚Šãƒ—ルーフ・オブ・ワークãŒå¿…é ˆã¨ãªã‚‹ãŒã€ãã‚Œã«ã‚ˆã‚Šé«˜ã„エãƒãƒ«ã‚®ãƒ¼æ¶ˆè²»ã¨å–引手数料ã¨ã„ã†é…延ã¨è²»ç”¨ãŒç™ºç”Ÿã™ã‚‹ã€‚é‡è¦ãªã®ã¯ã€ã“ã‚Œã¯ä»•æ§˜ã§ã‚ã£ã¦ãƒã‚°ã§ã¯ãªã„ã€ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã‚る。
- 金èžã®ã‚¢ãƒ³ã‚«ãƒ¼ã¨ã—ã¦ã®æ©Ÿèƒ½ã¯ä¹ã—ã„
- 金を模範ã¨ã—ã¦ã„ã‚‹ãŸã‚供給ãŒé™ã‚‰ã‚Œã¦ã„ã‚‹ãŒã€ãã®ãŸã‚ä¾¡æ ¼ã®å¤‰å‹•æ€§ãŒå¤§ããã€ä¾¡æ ¼ã®åŸºç›¤ã‚‚脆弱ã§ã‚る。良ã„金èžã®ã‚¢ãƒ³ã‚«ãƒ¼ã¯ã‚ˆã‚ŠæŸ”軟ã§çµŒæ¸ˆçŠ¶æ³ã«é©å¿œçš„ã§ã‚ã‚‹å¿…è¦ãŒã‚る。
- 支払ã„システムãŒéžåŠ¹çŽ‡çš„
- ãŸã ã€ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ãƒ–ルコインやトークン化ãªã©ã€ãƒ“ットコインãŒå¥‘æ©Ÿã¨ãªã£ã¦ã‚‚ãŸã‚‰ã•ã‚ŒãŸæŠ€è¡“ã«ã¯é‡‘èžã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ を変é©ã™ã‚‹å¯èƒ½æ€§ãŒã‚る。
- ビットコインã®ãƒ–ãƒãƒƒã‚¯ãƒã‚§ãƒ¼ãƒ³æŠ€è¡“ã¯ã€ŒäºŒé‡æ”¯æ‰•ã„å•é¡Œ*4ã€ã‚’解決ã—ã€ä»²ä»‹ã‚’経由ã—ãªã„安全ãªä¸€å¯¾ä¸€ã®å–引をå¯èƒ½ã«ã—ãŸã€‚ã—ã‹ã—ã€ä»¥ä¸‹ã®2ã¤ã®ç†ç”±ã«ã‚ˆã£ã¦å°†æ¥ã®è²¨å¹£ã¨ã¯ãªã‚‰ãªã„ã ã‚ã†ã€‚
- æš—å·é€šè²¨ã¯ãƒã‚¤ã‚¨ã‚¯ãŒæ£ã—ã„ã“ã¨ã‚’立証ã—ãŸã®ã‹ï¼Ÿ
- æš—å·é€šè²¨ã®å°é ã¯ã€ç«¶åˆã™ã‚‹æ°‘間通貨ã¨ã„ã†ãƒ•ãƒªãƒ¼ãƒ‰ãƒªãƒƒãƒ’・ãƒã‚¤ã‚¨ã‚¯ã®ãƒ“ジョンをè£ä»˜ã‘ãŸã‚ˆã†ã«ä¸€è¦‹è¦‹ãˆã‚‹ã€‚ã ãŒã€ãƒ•ãƒªãƒ¼ãƒ‰ãƒžãƒ³ã‚’ã¯ã˜ã‚ã¨ã™ã‚‹è‡ªç”±å¸‚å ´çµŒæ¸ˆå¦è€…ã‚‚èªã‚ã¦ã„るよã†ã«ã€é€šè²¨ã¨ã¯è‡ªç„¶ç‹¬å ã§ã‚ã‚Šã€ãƒãƒƒãƒˆãƒ¯ãƒ¼ã‚¯åŠ¹æžœã«ã‚ˆã£ã¦å˜ä¸€ã®ç™ºè¡Œè€…ãŒæ”¯é…ã™ã‚‹å‚¾å‘ãŒã‚る。暗å·é€šè²¨ã¯ã€ä¸»ãŸã‚‹äº¤æ›ã®åª’介や価値尺度ã¨ã—ã¦å›½å®¶ãŒç™ºè¡Œã—ãŸé€šè²¨ã«ç½®ãæ›ã‚ã£ãŸã‚ã‘ã§ã¯ãªã„。
- ãŸã ã€ç«¶åˆã®è„…å¨ã ã‘ã§é‡‘èžé¢ã®ã‚¤ãƒŽãƒ™ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ãŒã‚‚ãŸã‚‰ã•ã‚Œã¦ã„る。ãã®æ„味ã§ãƒã‚¤ã‚¨ã‚¯ã®ãƒ“ジョンã¯ã€ãŸã¨ãˆå®Ÿç¾ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒãªãã¦ã‚‚有用ãªæŒ‘戦ã¨ã—ã¦æ©Ÿèƒ½ã—ã¦ã„る。
- 自動æ“縦ã®é‡‘èžæ”¿ç–:デジタルé©å‘½ï¼Ÿ
- デジタル化ã¯ã€è²¨å¹£ã‚’インデックス化ã•ã‚ŒãŸä¾¡å€¤å°ºåº¦ã¨ã™ã‚‹ã€Œè‡ªå‹•æ“縦ã€ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ãªã©ã€è²¨å¹£æ”¿ç–ã®æ€¥é€²çš„ãªå†è€ƒã¸ã®æ‰‰ã‚’é–‹ã„ãŸã€‚
- アービング・フィッシャーã®ã€Œcompensated dollarã€ã®è€ƒãˆ*5ã¯ã€ãƒãƒªã®Unidad de Fomento*6ãªã©ã®ç¾å®Ÿä¸–ç•Œã§ã®å®Ÿé¨“ã«éƒ¨åˆ†çš„ã«åæ˜ ã•ã‚Œã€ã‚·ãƒ©ãƒ¼ï¼ˆ1998*7)もæå”±ã—ãŸãŒã€ã“ã‚Œã¾ã§ã®ã¨ã“ã‚ã‚ã¾ã‚Šæ³¨ç›®ã‚’集ã‚ã¦ã„ãªã„。
- ã“ã®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã§ã¯ã€è²¨å¹£ãã®ã‚‚ã®ãŒè²¡ãƒã‚¹ã‚±ãƒƒãƒˆã‚‚ã—ãã¯ã‚¤ãƒ³ãƒ•ãƒ¬ã«é€£å‹•ã—ã€ç©æ¥µçš„ãªé‡‘èžæ”¿ç–ã®å¿…è¦ã‚’減ã˜ã‚‹ã€‚デジタル化ã¯ã€ãƒªã‚¢ãƒ«ã‚¿ã‚¤ãƒ ã®èª¿æ•´ã‚„高ã„é€æ˜Žæ€§ã‚’å¯èƒ½ã«ã—ãŸã“ã¨ã§ã€ãã†ã—ãŸã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã®å®Ÿç¾å¯èƒ½æ€§ã‚’大ãã高ã‚ãŸã€‚
- ãŸã ã€é¡•è‘—ãªãƒªã‚¹ã‚¯ã‚‚ã‚る。
- ç¾åœ¨ã®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã¯å…¨èˆ¬çš„ã«ä¸Šæ‰‹ã機能ã—ã¦ãŠã‚Šã€å£Šã‚Œã¦ã„ãªã„ã‚‚ã®ã‚’ç›´ã™å¿…è¦æ€§ã«ä¹ã—ã„。
- å–引ã®å¤§åŠãŒåç›®ã§è¡Œã‚ã‚Œã¦ã„ã‚‹ã®ã«ã¯ç›¸å¿œã®ç†ç”±ãŒã‚ã‚Šã€ã‚¤ãƒ³ãƒ‡ãƒƒã‚¯ã‚¹åŒ–ã¯ãれを複雑化ã—ã€æœ‰ç”¨ãªç›¸ä¹—効果を失ã‚ã›ã¦ã—ã¾ã†ã‹ã‚‚ã—ã‚Œãªã„。
- 統計当局ã«ã‚ˆã‚‹ä¾¡æ ¼ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã®æ“作ã§å®Œå…¨ãªé€£å‹•åŒ–ãŒå¦¨ã’られるå¯èƒ½æ€§ã€‚
- å±æ©Ÿæ™‚ã®æœ‰ç”¨ãªãƒ„ールã§ã‚るサプライズインフレをä¸éŠ€ãŒä½œã‚Šå‡ºã™èƒ½åŠ›ãŒå¤±ã‚れる。
- ã¨ã¯è¨€ãˆã€é‡‘èžæ”¿ç–ã®è‡ªå‹•æ“縦ã¨ã„ã†è€ƒãˆã«ã¯ã€ãƒ‡ã‚¸ã‚¿ãƒ«çµŒæ¸ˆã«ãŠã‘ã‚‹ä¸éŠ€ã®å½¹å‰²ã‚’å†å®šç¾©ã™ã‚‹ã‚ˆã†ãªå°†æ¥ã®å¤§èƒ†ãªãƒ“ジョンをæ示ã™ã‚‹ã€ã¨ã„ã†ãƒ¡ãƒªãƒƒãƒˆã‚‚ã‚る。
- デジタル化ã¯ã€è²¨å¹£ã‚’インデックス化ã•ã‚ŒãŸä¾¡å€¤å°ºåº¦ã¨ã™ã‚‹ã€Œè‡ªå‹•æ“縦ã€ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ãªã©ã€è²¨å¹£æ”¿ç–ã®æ€¥é€²çš„ãªå†è€ƒã¸ã®æ‰‰ã‚’é–‹ã„ãŸã€‚
*1:cf. 40年を迎えた大平穏期:横断面分析から分かること - himaginary’s diaryã€熱を感じる:極端な気温と物価の安定 - himaginary’s diaryã§ç´¹ä»‹ã—ãŸè«–文(å‰è€…ã¯ä»Šå›žã®ã‚³ãƒ©ãƒ ã§ã‚‚å‚ç…§ã•ã‚Œã¦ã„る)。
*2:cf. å‰æ³¨ã®å‰è€…ã®è«–文。
*3:cf. 高額紙幣の廃止とマイナス金利政策 - himaginary’s diary。
*4:cf. Double-spending - Wikipediaã€Double-Spending in Cryptocurrency: Definition, Risks, and Prevention。
*6:cf. Unidad de Fomento - Wikipedia。
*7:Indexed Units of Account: Theory and Assessment of Historical Experience | NBER。